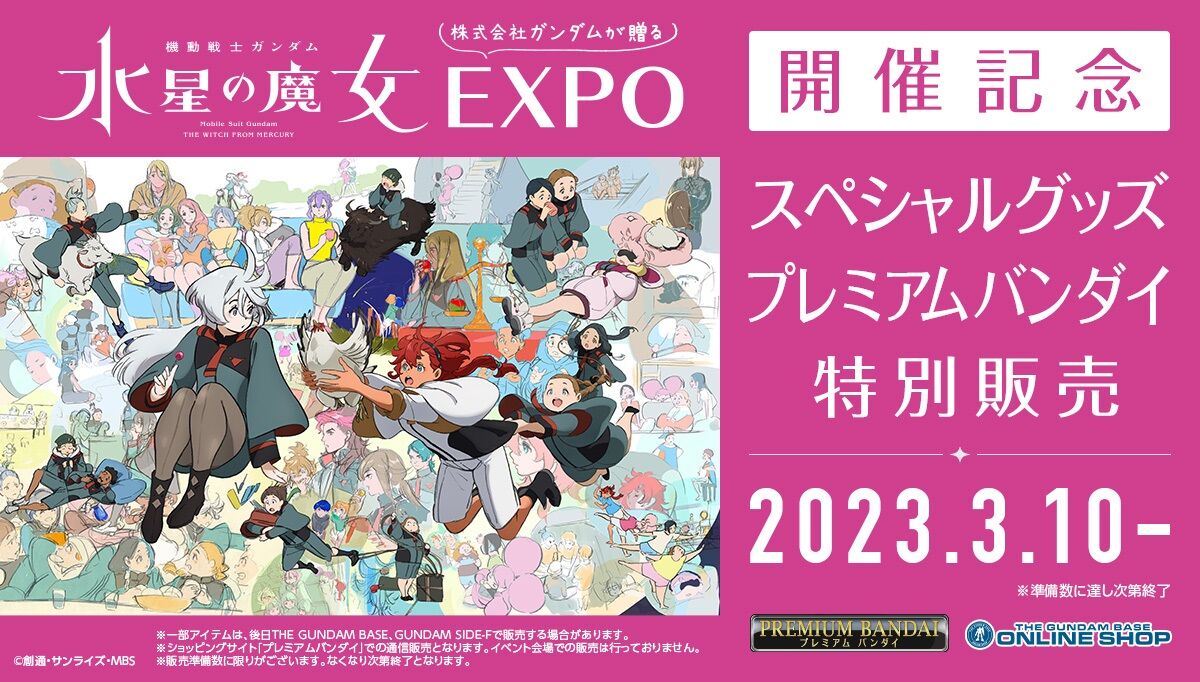DTM(デスクトップミュージック)は急速に進化しており、ノートパソコンやタブレットを使用して、いまやデスクトップを越えて場所を選ばず作曲やミキシングをすることができるようになってきています。DTMをポータブルする際の唯一の障害であったオーディオインターフェースもAntelope Audio Zen Go Synergy Coreのようなポータブル式の高性能機の登場によって、課題ではなくなりました。
そうしてあらゆる課題をクリアした後、DTMerにとっての懸案事項は、最終的なサウンド出力の正確性です。持ち運べるくらいパーソナルでコンパクトなDTM環境を構築することを考える場合、たとえニアフィールドの小型機種であってもモニタースピーカーを持ち歩くというのは現実的ではありません。
あなたがポータブル性を考慮していないにしても、都会の狭い防音処理も不完全な住居空間で深夜まで作曲に没頭するのを考えた場合、スピーカーは場合によって家族や隣人といった周囲に迷惑をかけることもあります。かといって音量を小さくしてしまえば、十分なイメージングを得られず、作曲作業が停滞するということもあるでしょう。そのため、とくに予算と環境が限られる駆け出しから中級までのDTMerにとってヘッドホンやイヤホンが必須アイテムとなります。
DTMerの予算は限られていますが、必要なものは非常に多様です。DTMのメインソフトウェアとなるDAWだけでなく、EQや音源を提供するVSTプラグイン
、楽器
、アナログアンプ
、コンプレッサー
、オーディオインターフェース
など作曲の幅が広がるにつれて出費もかさみます。そのため、多くのDTMerは限られた予算を効率的に投資したいと願っています。同時にDTMerにとって時間は命です。主業ではない趣味としてDTMをしているDTMerにとって、通勤の間などといった隙間時間を少しでも作曲に使いたいという気持ちは常にあります。
DTMerを悩ませる、予算と時間配分、そしてポータブル性に関する問題を解決するために、より安価で優秀なヘッドホンやイヤホンが必要になります。この記事ではDTMの入門者を対象にして、高価なモニタースピーカーに勝るとも劣らないイメージングをより安価に提供するイヤホンやヘッドホンを紹介します。
- イヤホンやヘッドホンで作曲して大丈夫?実はスピーカーよりヘッドホンやイヤホンの方が利点が多い
- 安価な予算でDTMerに本当に必要な音を実現するイヤホン、ヘッドホン
- Superlux HD668B(コスパ最強の自由音場系スタジオチューニングモニターヘッドホン)
- Classic Pro CPH7000(入門者からスタジオレコーディングまで使えるコスパ最高のモニターヘッドホン)
- JVC HA-AE5T(高解像かつワイドレンジの卓越したサウンド)
- Tripowin Lea(中域の完璧な再現)
- Behringer MO240(ニアフィールドモニターサウンドを廉価に耳元で再現)
- AUDIOSENSE T180(完全な自由音場系スタジオモニターサウンドの再現)
- EarFun Air Pro 2(広い音域にわたって実現されたスタジオニュートラルサウンド)
- SoundPEATS T2(重低域にこだわる人に必須)
- 【関連記事】
イヤホンやヘッドホンで作曲して大丈夫?実はスピーカーよりヘッドホンやイヤホンの方が利点が多い
一昔前、プロのサウンドエンジニアにとってはヘッドホンはあくまで補助のオーディオ機器でした。音楽はスピーカーで聴くものというのが常識であり、実際に現在でも多くの音楽はスピーカーで聴くことを前提としたステレオ録音がされているため、サウンドエンジニアはスピーカーとは異なるヘッドホンの定位感を嫌悪しさえしていました。
よく知られているように、現実空間を利用して音像を定位させるスピーカーとは異なり、ヘッドホンやイヤホンの音は頭の中に音像が形成される、頭内定位を引き起こします。現在のステレオ録音音源は、スピーカーのように人体の外側の物理空間を利用して音像を形成する機器を前提に録音されているため、ヘッドホンやイヤホンのような左右の耳に固定された機器で聴くと、スピーカーで聴く場合には当然ある音像との距離感が失われて、頭の中心付近から音像が展開されます。この頭内定位を、サウンドエンジニアや研究者はヘッドホンやイヤホンの問題点として長年課題としていました。
しかし、サウンドエンジニアや研究者がいうほどには頭内定位の問題は実際は重要ではありません。よく考えてみてください。もし頭内定位の問題が音楽のイメージングに致命的な影響をもたらし、人がそれでステレオ録音の音楽を聴くのに不便さや不快さしか感じないならば、イヤホンやヘッドホンはとっくに絶滅しているはずです。ところが実際には、イヤホンやヘッドホンは市場を拡大しています。
頭内定位の問題自体も近い将来かなり解決する目処が立っているようです。
イヤホンやヘッドホン、とくにカナル型イヤホンにはスピーカーにない利点もあります。物理的な空間を利用して音像を展開するスピーカーのサウンドには必然的にクロストークが存在します。理想的なステレオイメージを形成する2chスピーカーは左側のスピーカーの音は左耳だけに、右側のスピーカーの音は右耳だけに聞こえる必要がありますが、実際は両耳に左右のスピーカーの音が混在します。これを両耳間クロストークと言います。これにより過渡応答が大幅に悪化することが知られていますが、カナル型イヤホンはスピーカーと異なり、耳道に直接挿入され、左右の音がほぼ完全に独立して鼓膜に到達します。そのため、この両耳間クロストークが無に等しく、優れた過渡応答が実現され、立体的で正確な音像形成に有利です。スピーカーでは両耳間クロストークを解消するために厳密な空間セッティングとクロストーク・キャンセル機能といった補助が必要となりますが、ヘッドホンやイヤホン、とくにカナル型イヤホンでは特別な処置なしに両耳間クロストークの問題が解決されます。
実際に両耳間クロストークが音像形成にどのような影響をもたらしているかについては以下の記事でわかりやすい解説があり、さらにクロストーク・キャンセルの効果を擬似的に体感できます。
ステレオ再生において,ステレオスピーカーとリスナー両耳間では,クロストークを生じます。両耳間クロストークは,アンプ内部等におけるクロストークに対してはるかに高レベルで,音質・音場に重大な影響を与えます。特に再生音場を左右スピーカーを結んだ直線上に矮小化すること,および左右スピーカーの発する単一音が,リスナー両耳に時間差をともなって聴取されることによる過渡特性の低下は,重大です。両耳間クロストーク(以下,たんにクロストークと表記します)対策は3つあります。
1)スピーカー間隔を取る。
2)再生音場をマルチchでサラウンド化する。
3)クロストークを打ち消す。
しかし 1)では低音域ほどクロストークが残って過渡特性はむしろ悪化し, 2)では音場感は拡大するものの過渡特性が改善されません。望ましいのは本来 3)です。https://www.jas-audio.or.jp/journal-pdf/2008/08-09/200808-09_010-014.pdf
音場形成の上でもイヤホンやヘッドホン、とくにカナル型イヤホンはスピーカーに比べて有利です。スピーカーによって人体外の物理空間を利用して音源の音場(原音場)を形成することを考えると、理論上空間全てをスピーカーの音で満たす必要があります。したがって、スピーカーは音楽の広さを実現するために物理的に多数のch数を必要とします。これに対してカナル型イヤホンは音場形成に両耳しか必要とせず、人体外の物理空間を必要としないので、理論上2chのみで原音場の再現が可能です。
耳の穴に挿して使うカナル型イヤホンは音像定位と解像度を両立できる唯一の解とみられる。但し音像イメージは頭の中に展開する不自然さががあり課題になっている。
したがってDTMerにとって実際はスピーカーよりヘッドホンやイヤホンの方が技術的な利点が多いわけですが、それでも頭外定位するスピーカーでの再生を前提としたステレオ音源の作曲にヘッドホンやイヤホンの定位感は不利だと主張する人もいるでしょう。しかし、日本ではほとんどの人がステレオ録音音源をイヤホンやヘッドホンで鑑賞している現実を思い起こせば、リスナーがイヤホンやヘッドホンを選んでいる現状で、作曲側がスピーカーにこだわる限り、ギャップを埋めることはできないという事実を知るべきです。むしろ最先端のDTMerは優れたヘッドホンやイヤホンを使いこなし、多様なアプローチで作曲に臨むことで、創造性を無限の音場に拡大することができるでしょう。スピーカーで音場のすべてを把握することは困難ですが、イヤホンとヘッドホン、とくにカナル型イヤホンならそれがほとんど可能なのです*1。
まとめると、
- 音像と音場両方の把握において、スピーカーよりヘッドホンやイヤホンの方が優れている
- 頭内定位の問題は多くの人が実際上それに慣れており、再生環境もイヤホンやヘッドホンを使っている人が多いので、無視できる
- イヤホンやヘッドホンはスピーカーのように物理的な空間セッティングを気にする必要がない
- イヤホンやヘッドホンはスピーカーと違って持ち運びやすく、すぐ使える
- イヤホンやヘッドホンは周囲への騒音源になりにくいので、安心して使える
つまり、DTMerにとってイヤホンやヘッドホンを使う方が利便性が高いのです。
安価な予算でDTMerに本当に必要な音を実現するイヤホン、ヘッドホン
さて、理論的な話はもうやめにしましょう。今度は実用的な話です。この記事では入門者から中級者のDTMerにとってかけがえのない相棒となる優秀なモニター機器をイヤホン・ヘッドホン問わず、その使い方と特徴とともに説明します。価格帯は1万円以内です。その中にはメジャーメーカー製の有名な機種はありません。基本的には一部を除いてDTMerが聴いたこともないような機種でしょう。
まさかとは思いますが、1万円以内という価格ではとてもハイエンドクラスに匹敵するサウンドを手に入れることができないと思ってませんか?そうだとすれば、邪悪なオーディオ資本主義に毒されているとしか言いようがありませんね。私から言わせれば、ただ贅沢な素材やドライバーの数を増やしただけのハイエンド機種の多くは、実際のオーディオスペックはゴミのようであり、調整不足の狂ったインピーダンス特性のせいでまともに鳴らすのすら困難なものがざらにあります。肝心のサウンドチューニングが良ければ話は別ですが、これまた個人的趣味を追求したかのような意味不明でお粗末なものばかりなので、それらはただ単に音楽を破壊するだけです。せっかくいい素材を使っているのにクソみたいな音を聞かされたら余計に幻滅しますよね。私がこれまで聴いてきたハイエンド機種の多くは一部だけ不自然なほど妙に良く聞こえるので、気持ち良いところもありますが、よく聞くとサウンドバランスが破綻しているのですぐ飽きる、そんなのばっかりです。
多くの人が忘れがちですが、ハイエンド機種の多くは実験的であり、堅実で十分に熟れた技術が使われているわけではありません。DTMerに必要とされる正確無比なサウンドを提供するのはむしろ堅実で安価に提供されている蓄積された技術と、それによって浮いた手間をかけてよく研究されたチューニングで作られた低価格機種のほうです。現状のオーディオ業界のこの奇妙な逆転現象(低価格機種に総合的な音質で優れているものが多い)はもっと知られてよいでしょう。(この話にもっと興味がありますか?あなたはここで私と同じ結論にたどり着いた人を見つけることができます。)
このリストには、あなたの普段使っている有名機種や雑誌や口コミでよく聴く機種が載っていませんか?思わず笑ってしまい恐縮ですが、いまだにそんなくだらないものを信じているのですか?
たとえば、ある商品について、Twitterでのたくさんの口コミを見て、人気があると思ってすぐ商品を買ってしまう癖がある人は要注意です。こうした投稿の動機の内訳についての調査がありますが、よく読んでみると、実態がわかりますよ。
twitterなどのSNSの口コミは実際には新手の大規模に行われる客引きのようなもので、話題作りのために行われているものです。たとえそれが個人アカウントが行ったものであっても、実際には発信者側にメリットがあるから行っているものが多く、それを見た側のメリットを考えて行われているものはほとんどありません。テレビ通販の「使用者の声」をたくさん聴かされる進化版みたいなもんです。
もちろん、だからすべてが悪いというわけではありませんが、Twitterの口コミに何か客観的な信頼性があると考えているなら、実際にはそんなものはほとんどなく、作為的に拡散された情報が出回っているということを知っておくのは良いかもしれませんね。Twitterは知識がなくて騙されやすく、感情や雰囲気、流行に流されやすい若年層や情報弱者をターゲットにしたマーケティングが最も大々的に繰り広げられている場所です(twitterの面白い点は重度のツイッター依存者の方が実際はツイッターに時間的に支配され、情報経路が非常に限定されてしまっている情報弱者にもかかわらず、情報強者だと思い込んでいることですが、この記事の主旨からは外れるので割愛します)。
この記事で紹介するのは本当に使える機種だけであり、評価するのは人気ではなく、純粋にオーディオ的に優れているものだけです。
Superlux HD668B(コスパ最強の自由音場系スタジオチューニングモニターヘッドホン)

DTMerに廉価で素晴らしいサウンドを実現する音響機器を紹介するためのこの記事で、先駆けにふさわしいのはこのヘッドホンしかありません。日本ではほとんど無名に近い台湾メーカーのモニターヘッドホンSuperlux HD668BはAudioScienceReviewをはじめ、多くのオーディオレビュアーを感嘆させ、その中には私も含まれます。きわめてフラットなインピーダンス特性を持ち、自由音場フラットに忠実でありながら、同時にスタジオチューニングリファレンスニュートラルターゲットの水準も満たす、音質的にはほとんど欠点のない機種です。そして価格は5000円以下です。
もしあなたがSONY MDR-M1STを使っているのなら、そんなゴミは売り払って、いますぐこれを買いましょう。ミキシング、トラッキング、レコーディングほぼすべての面で改善が見込めます。冗談かって?私は真顔です。
欠点は装着感とチープな外観と開放型独特の音漏れだけです。しかし、高価なモニターヘッドホンやモニタースピーカーに匹敵するサウンドがわずか5000円に手に入るのですから、気にするほどのことではありません。
コスパ最強モニターヘッドホンの一角、#Superlux HD668B先生
— audio-sound @ hatena (@audio_sound_Twr) 2021年9月20日
ケーブルのコネクタはこんな感じだから、
amazonでたくさん売っている安いワイヤレスオーディオレシーバーを買ってくれば、 pic.twitter.com/98OdAYM1Q6
こんなふうにすぐにワイヤレス化できてしまうところは便利 pic.twitter.com/q67uwAHWTv
— audio-sound @ hatena (@audio_sound_Twr) 2021年9月20日
ちと目立つし、プラプラするけどw pic.twitter.com/EsUMimCu7B
— audio-sound @ hatena (@audio_sound_Twr) 2021年9月20日
使い道
- ミキシングチェック
- 広い音域のディテールとバランスの確認
- レコーディング品質のモニター
- スタジオトラッキング
欠点
- 低域のディテール
- ビルドクオリティ
Classic Pro CPH7000(入門者からスタジオレコーディングまで使えるコスパ最高のモニターヘッドホン)

低価格で本格的なレコーディングやDTMに耐えうるスタジオモニターが欲しい場合、Classic Pro CPH7000はまっさきに検討すべきヘッドホンの一つです。サウンド面では1万円以上の多くの優れたモニターヘッドホンと競合するポテンシャルを秘めており、とくにハーマンサウンドを重視するリスナーにはEQで微調整するだけでそれに限りなく近づけるため、魅力度はさらに高いでしょう。
入門者に最適で、長く使えるモニターヘッドホンであり、文句なくおすすめできる逸品です。長く日本のスタジオシーンやイベントシーンを支えてきたサウンドハウスだからこそ作れたと言える、誇れる優れたスタジオモニターヘッドホンです。
CPH7000はDTM初心者の初期投資のマネージメントに大きく貢献する理想的なモデルで、これを買うことでモニターヘッドホン選びに迷うことなく安上がりに済ませ、ほかの機材にお金をかけることが出来ます。入門者がプロになるまで使い続けられる5,000円以下の機材というのは稀ですが、CPH7000はそうした機材の数少ない一つです。
使い道
- デジタルで緻密な構成の楽曲の作曲、編曲
- ミキシングチェック
- レコーディングチェック
- スタジオトラッキング
欠点
- 低域のディテール
レビュー記事:
JVC HA-AE5T(高解像かつワイドレンジの卓越したサウンド)

日本の実力派オーディオブランドのスポーツモデル完全ワイヤレスイヤホン「JVC HA-AE5T」は優れたバランス感覚のワイドレンジ高解像サウンドを持っており、ハイエンドクラスに匹敵する透明度で中域を描写することができる優秀な完全ワイヤレスイヤホンです。
低域増幅モードで低域を増やして聴くことができるため、クラブでの音の聞こえ方に近い雰囲気での音源チェックも可能ですし、低域を作りこむときにも重宝します。
また、スポーツモデルらしく、耳にしっかりと固定される装着感も魅力で、少し激しいパフォーマンスをしても耳から外れることはなく、完全ワイヤレスですからケーブルもないため、演奏や歌唱のモニターとしても使いやすい製品です。配信の際にも活躍してくれ、DJモニターとしても優秀です。
使い道
- 低域から中域のミキシングチェック
- レコーディングチェック
- スタジオトラッキング
- マスタリングチェック
欠点
- 高域のディテール
JVC HA-AE5Tのレビュー記事:
Tripowin Lea(中域の完璧な再現)

Tripowin Leaはわずか3000円程度で買えるイヤホンですが、非常に優れて透明な中域を持つイヤホンです。あらゆる楽器やボーカルの質感と立体感が高解像度でかなり忠実に再現されるため、楽曲の心臓部の作曲、ボーカルチェック、レコーディングチェックなどで比類ない性能を発揮します。
弱点は低域と高域がやや弱いことで、これらの音域を作りこむときにやや信頼性が低くなることです。
また制動特性が安定しているため、音源機器を選ばずに駆動でき、スマホでも解像度の高い音で音楽をチェックできます。次に紹介するBehringer MO240とは相互補完関係にあり、MO240は中域の信頼性に欠け、高域と低域はかなり信頼できます。
使い道
- デジタルで緻密な曲の作曲
- 中域のミキシングチェック
- 中域のレコーディングチェック
- スタジオトラッキング
欠点
- 高域および低域のディテール
Tripowin Leaのレビュー記事:
Behringer MO240(ニアフィールドモニターサウンドを廉価に耳元で再現)

競合他社に匹敵あるいは勝るような品質の類似製品をより廉価に提供することに生き甲斐を見出しているようなメーカーがBehringerですが、イヤホン製品でもその精神は変わっていません。1万円未満の非常に廉価で手に入る製品にも関わらず、MO240には理想的なモニターイヤホンに必要なものがほぼすべて備わっています。すなわち、高い原音忠実性、わかりやすい定位感、フラットなインピーダンス特性、広い音域、低い高調波歪み、そして現実のモニタースピーカーに近いサウンドです。
Behringer MO240は低域から中域までは自由音場フラットに非常に忠実で、モニタースピーカーと同じ再現性を持ち、現実のスピーカーと同じように奥行き感が少し強調されています。最後の高域は詳細なディテールを提供するスタジオチューニングに近い調整です。
Behringer MO240は今のところ絶望的に知名度が低く、販路も限られているために全く話題になっていませんが、一度このイヤホンを手に入れた後は、大抵のDTMerがイヤホンに1万円以上払うのが馬鹿らしくなるでしょう。多くのイヤホンがこのイヤホンほど十分なステレオイメージを提供しないことに呆れるはずです。
このイヤホンの驚異的な点は、接続する音響機器を選ばない点です。スペック値が秀逸で、スマホでもわりと十分に鳴らせる上に、ハイブリッド機種にも関わらず、大食いのスタジオヘッドホン向きのパワー重視のヘッドホンアンプでもサウンドバランスがほとんど崩れないインピーダンス特性になっています。したがって、MO240はスタジオでも通勤中でも場所を選ばず、いつもの理想的な正確無比のモニターサウンドをつねに提供します。
先に紹介したTripowin Leaとは補完関係にあるようなサウンドになっています
使い道
- ミキシングチェック
- 広い音域のディテールとバランスの確認
- レコーディング品質のモニター
- スタジオトラッキング
欠点
- ボーカルチェックに向かない
Behringer MO240のレビュー記事:
AUDIOSENSE T180(完全な自由音場系スタジオモニターサウンドの再現)

シングルBAのAUDIOSENSE T180は低域から中域にかけて自由音場フラットに近く、高域でスタジオチューニングのディテールサウンドを実現しており、ややウォームでき着心地も安定している、正統派に近いモニターサウンドを持っています。
しかし、高調波歪みは緻密な作曲に使えるほどには低くないので、全体的なオーディオスペックはMO240に劣りますが、自由音場により忠実なため、中域ではより正確な音像定位感と明瞭性を提供します。レビューにも書いておりますが、駆動次第では全体的なサウンドをより高精細なモニターに変化させることも可能です。
ほぼ同様のサウンドを提供するUGREEN Hituneと同じように、ボーカル品質の確認、中域のミキシングモニター、トラッキングモニターとして優秀な機種で、ボカロ曲のようなスピード感と精巧な情報量を重視する楽曲の作曲にも向きます。
使い道
- デジタルで緻密な構成の楽曲の作曲、編曲
- 中域のミキシングチェック
- 中域のレコーディングチェック
- トラッキング
欠点
- インピーダンス特性のせいで音響機器を選ぶ
- 低域のディテール
AUDIOSENSE T180のレビュー記事:
EarFun Air Pro 2(広い音域にわたって実現されたスタジオニュートラルサウンド)

10万円以上のイヤホンを買うことに熱中する悪い癖がありますか?ではそれを買って余ったお金でEarFun Air Pro 2を買っておきましょう。悪い買い物癖が収まるかもしれませんね。EarFun Air Pro 2は優れたスタジオチューニングニュートラルサウンドを提供する優秀な機種です。DTMerとして少し経験を積んだ人であれば、低域から高域まで細かな音を丁寧にバランスよく拾うそのサウンドに驚きを隠せないでしょう。ボーカルは非常に自然で、楽曲全体のコントラスト感もよく、正確なステレオイメージと質感でニュアンスも豊かに拾うことができます。
この完全ワイヤレスイヤホンは強力なアクティブノイズキャンセリング機能も搭載しており、1万円以下で買えるにもかかわらず、現状の2万円以上の完全ワイヤレスイヤホンのほとんどを音質、ANC性能ともに凌駕します。そんなことあるわけないって?いや、これは私の測定値に基づく単純な事実です。DTMerが求めるほぼすべてのものがフルワイヤレスで実現されているという事実はもっと広く知られてよいでしょう。
まあ、あなたが私と同じく澤野弘之氏を尊敬しており、彼が使っているというGenelecのモニタースピーカーをステータスとしてほしいという場合は私も同じ性質の人間なので止めはしません。しかし、それ以外の多くの中級DTMerに必要なのはGenelecではなく、EarFunのこのイヤホンです。その余ったお金でよりよいオーディオインターフェースを揃えましょう。
使い道
- ミキシングチェック
- 広い音域のディテールとバランスの確認
- レコーディング品質のモニター
- スタジオトラッキング
- 低域のバランス/ディテールチェック
欠点
- ほぼなし
EarFun Air Pro 2のレビュー記事:
SoundPEATS T2(重低域にこだわる人に必須)

DTMerだけでなく、プロの作曲家、サウンドエンジニアでも最も苦労するのが低域です。多くのモニタースピーカーやヘッドホン、イヤホンは30Hz付近まで音がしっかり聞こえるチューニングにはなっていません。しかし、SoundPEATS T2のANCモード時のサウンドは15Hz付近までかなり低い高調波歪みで階層性のしっかり聞こえる環境を提供します。そうです。もう低域のディテールが聞こえなくて苦労するなんてことはなくなります。ここまではっきり低域が聞こえるのですから、「よく聞こえなくてうまくミキシングできなかった」なんて言い訳もできなくなります。
欠点が多い機種ですが、重低域の作り込みにこだわるなら、このイヤホン以外の選択肢はほぼ皆無です。ええ、書き間違いではありません。スピーカー、イヤホン、ヘッドホン、全機種全価格帯見てもほぼ皆無という意味です。
使い道
- ほかの機器ではほぼ不可能な超重低域のサウンドチェック
欠点
- 全体印象が低域に影響されすぎる
- ANC時にときどき入る露骨なノイズ
SoundPEATS T2のレビュー記事:
【関連記事】
*1:蛇足かもしれませんが、JASジャーナルに掲載された西尾文孝氏の「空気録音」についての検証レポートも重要な示唆を与えてくれます。