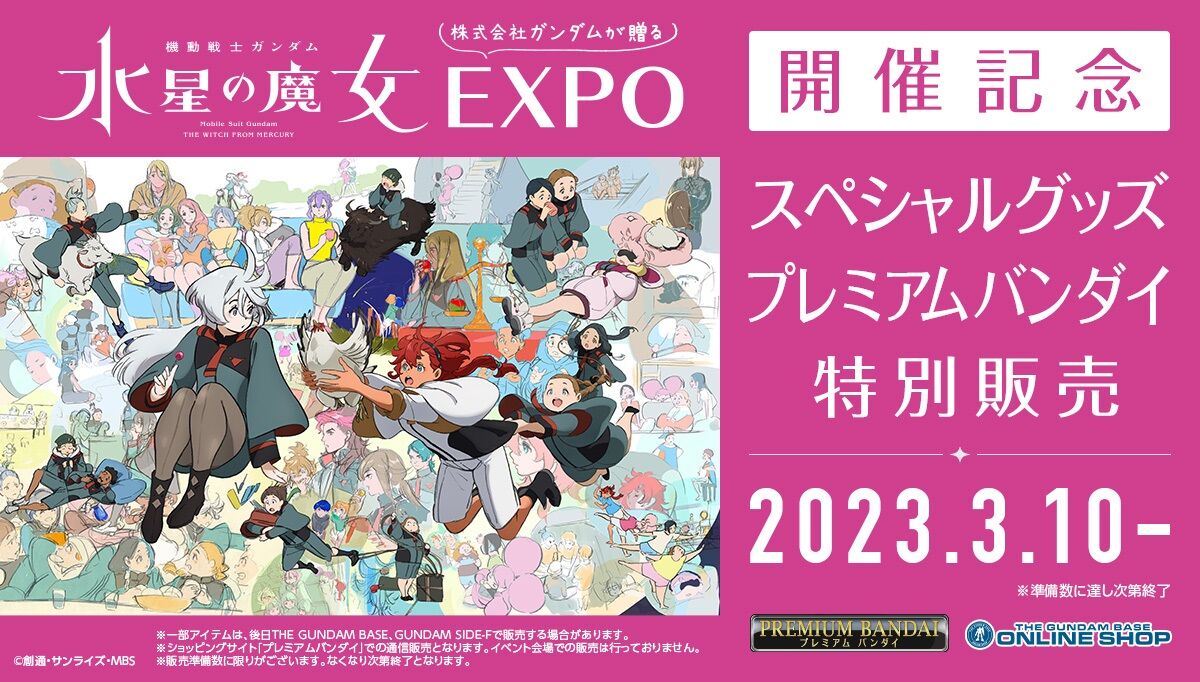「フラッシュレビュー」はデータ中心の簡潔な内容で、ポイントを絞ってオーディオ製品を解説します。
今回取り上げる中華イヤホンの機種はTri Starseaです。
TRIはKBEarの姉妹ブランドであり、手頃な価格帯でハイエンドに匹敵する高品質なオーディオギアを製造しています。ほんの数ヶ月前に、彼らは4つのEST(静電型)ドライバーを備えた強力な7ドライバーハイブリッドセットアップを備えたフラッグシップモデル TRI Starlightをリリースしました。Starlightは多くの注目を集め、その素晴らしいパフォーマンス、人目を引くルックス、そして財布に優しい価格設定でありながらプレミアムパフォーマンスを実現し、賞賛されました。
audio-sound @ hatenaはこの機種を「audio-sound @ hatena Highly Recommended」として、大多数の人にとって満足度が高いオーディオ製品であると推奨します。
基本スペック
- ドライバー構成:1DD+2BA
- 周波数特性:20Hz~20kHz
- インピーダンス:9.5Ω
- 感度:106 + 2dB
- ケーブルコネクタ:0.78mm 2pin
パッケージ
パッケージは価格帯ではかなり豪華です。というよりフラッグシップのTri Starlightと同等のパッケージです。Starlightは価格の割に物足りない気がしましたが、1万円台ですと、わりと上質に思えます。
本体のビルドクオリティは価格帯では標準以上で、フェースプレートが非常にかっこよく、似たような雰囲気のqdc Uranusに比べると、「いかにもプリントしました」といった感じのUranusよりこちらのほうが かっこよく見えるくらいです。両者は音質的にもナチュラル系のサウンドで購買層が被る気がします。そしてUranusよりStarseaのほうがバランスがニュートラルに近く万能です。





装着サンプル
ユニバーサルIEMタイプで耳への収まりは良好で、遮音性も良好に思えます。



音質
測定機材
- SAMURA HATS Type3500RHRシステム:HEAD & TORSO、左右S-Typeイヤーモデル(Type4565/4566:IEC60268-7準拠)
- AWA社製Type6162 711イヤーシミュレータ
- マイクプリアンプ:Type4053
- Type5050 マイクアンプ電源
- オーディオインターフェース:ROLAND Rubix 24
- アナライザソフト:TypeDSSF3-L
※イヤーシミュレーターの特性上、20hz以下と16khz以上の信頼性は高くありません。
周波数特性
この機種には音質変更スイッチがついていますが、以下はデフォルトのexquisite pure toneに設定して測定しています。
上から順に、
- [標準イヤーピース(黒) S装着時]左右別
- [標準イヤーピース(黒) S装着時]左右平均
- [標準イヤーピース(黒) S装着時]左右別(自由音場補正済み)
- [標準イヤーピース(黒) S装着時]左右平均(自由音場補正済み)
- [標準イヤーピース(赤軸) S装着時]左右別
- [標準イヤーピース(赤軸) S装着時]左右平均
- [標準イヤーピース(赤軸) S装着時]左右別(自由音場補正済み)
- [標準イヤーピース(赤軸) S装着時]左右平均(自由音場補正済み)
- [標準イヤーピース(緑軸) S装着時]左右別
- [標準イヤーピース(緑軸) S装着時]左右平均
- [標準イヤーピース(緑軸) S装着時]左右別(自由音場補正済み)
- [標準イヤーピース(緑軸) S装着時]左右平均(自由音場補正済み)
- イヤーピース比較(自由音場補正済み)
※当ブログの自由音場補正については機材に合わせてサザン音響さんから提供された補正値を使用しております。













サウンドシグネチャー解説
全体はほとんどニュートラルです。わずかにウォーム寄りかなと思える、穏やかなU字型です。聴き心地は安定していますが、こういった、ほぼニュートラルで長く、起伏も少し大きいW字型のような形で高域のピークと深い低域があるサウンドは、曲によって少し印象がぶれやすいところがあるので、聴く曲によっては音がいつもより繊細に聞こえたり、逆に暖かく聞こえやすいところがあります。装着感や音量差での変化もあるので、人によって案外と印象が違って聞こえたりする可能性があるでしょう。とはいえ、総合的にはバランス感覚に優れていて、フラットに近い聴き心地を楽しめるだろうと言えます。
THD+N特性
マガジン専用コンテンツになります。
音質解説
低域は深いところまで伸びており、階層的に聞こえます。この形の低域は最近批評的なオーディオファンの間ではわりと好まれている形で、モニターフラットに近い雰囲気を維持しながら、深さを出せるので、中域を広く感じることができ、しかも低域の熱気を少し引き出すのでウォームで聴き心地が安定するという利点もあり、定番の形です。あとから比較しますが、この機種で中域から低域の傾斜はライバルとなるFiiO FH3よりゆるやかになっており、よりナチュラルでノイズ感も少ないです。低域ジャンキーの私が言うのも何なのですが、中域主体で考えた場合、たとえばエレキベースの強いロックを聴くと、FH3の低域は中域をわずかに邪魔しやすく、私が最終的にはFiiO FH3よりMangird Teaの方が好きなのもここらへんに原因の一つがありそうです。もちろんFiiO FH3のほうがライブ感があって良いと肯定的に評価することも可能ですが、TeaやStarseaのような低域の方が、音楽の全体の中では収まりが良いでしょう。
中域は静寂感と空間の清潔感は充分で、ボーカルの周辺には少し広いマージンを感じます。ボーカルは少し明るく前進しており、人によってわずかにシャウティに感じられる可能性がありますが、概ねナチュラルで聴き心地は安定しています。ただし音量を上げるとボーカルはどんどん元気に前に出てくるので、少しうるさくなりやすいところがあります。ボーカル周りは清潔で中域は見通しが良好です。静寂感も適切で、多くの人の適正音量でピーキーになることはありません。
高域の構造もよく出来ていて、中高域をピークを作らない程度にゆるやかに少し強調しつつ、高域は中域と良くバランスの取れる位置まで伸びています。空間は中域で風通しが良いですが、超高域の余韻は適度に抑えられているので、音場は開放的すぎず中域へスポットライトが当たります。高域は人によってアコースティックギターのエッジやハイハットにわずかに派手なギラつきや尖った印象を感じる可能性はありますが、個人的には多くの場合、輝度に対して適切な明度を保っているように思われます。非常にバランス感覚が良く、FiiO FH3よりナチュラルな高域の雰囲気はどちらかというとqdc Uranusのような音に近く、滑らかでシームレスに感じられます。
はっきり言って、FiiO FH3やqdc Uranusあたりの一流機種と同等以上のパフォーマンスが期待できます。
音質スイッチの効果について

まあ、なんかスイッチみたいなものが付いているので、その効果について気になるかも知れません。興味のある人のために有料記事で詳しく検証しています。
FiiO FH3/qdc Uranusとの比較
さて、この機種を私なりに形容すると、「FiiO FH3のような優れた音域バランスとqdc Uranusのようなピーク感のない滑らかでシームレスな自然なサウンドの特性をちょうどいい塩梅でブレンドしたような機種」と言えます。長いw
実際のところ、私はTriのチューニングがわりとハズレが少ないということも知っており、今回も半ば惰性で注文しましたが、世間ではわりと好評だったらしいTri Starlightはあんまり好きじゃなかったので、それほど期待してませんでした。外観とパッケージは良さそうだったのでその点は心配ありませんでしたが、このブランドにはQoAやKinera、DUNU、Moondropほど全幅の信頼を置いてないので、ワクワクして待っていたという感じではありませんでした。しかも、新興メーカーのくせにノズル交換だスイッチだなんて音質変更手段らしきものを安易に付けているような類いのイヤホンを、私は個人的にわりと信頼してません。しっかりしたメーカーのものと違い、新興メーカーはこういう音質変化オプションを適切に作り込むことはできないことが多いと経験的に思っているからです。個人的には穿ってしまうところがあるので、チューニングで迷ったのをごまかすための方便に使っている可能性すら考えてしまうくらい。
しかし、実際届いてみるとかなり均整の取れたチューニングでTriらしいウォーム感も維持されており、音の質感も自然で、1万円台のホープになり得ることは断言できます。

さて比較してみるとまず顕著なのがqdc Uranusです。その厚く豊かで充実感と重厚感のあるサウンドは他機種に比べると高級感の感じられるサウンドですが、人によっては中域が濁る印象を受けてうるさいでしょう。モニター的な音が好きな場合はとくにそう感じるはずです。リスニングイヤホンとしてはUranusは優秀ですが、IEMを好む批評的なオーディオファンの好みからは少し外れる可能性が高いです。Uranusはピーク感も少なく、穏やかかつ滑らかに、色づきよく音楽を聴かせてくれますが、音場は少し狭く思う可能性があります。
FiiO FH3は非常に均整の取れた3つの山を持っており、明瞭感もモニターサウンドとして充分な明るさを持ちつつ、リスニングイヤホンとしても落ち着いて聞け、音場も適度に広いという美点があります。一方でTri Starseaのほうはもうちょっと中域が広く、明瞭感はほぼ同等でも輝度が高めで、もう少し繊細でシャープにしゃっきりしたサウンドに聞こえます。歪みの少なさはほぼ同等ですが、わずかにFiiO FH3のほうが優れているでしょう。
録音比較
浮遊大陸アルジェス -Introduction-(OST系)
浮遊大陸アルジェス -Introduction- / Zwei!!オリジナル・サウンドトラック2008 / Copyright © Nihon Falcom Corporation
レコーディングシグネチャー
レコーディングシグネチャーの基本的な原理、楽しみ方については以下を参考にして下さい。
参考用にレコーディングシグネチャーを掲載します。ソースはFiiO M15を用いています。イヤーピースは標準イヤーピース(緑軸) Sサイズを使い、スイッチはexquisite pure tone、ゲインは低設定です。
レコーディングシグネチャーで使用している楽曲は私も大好きなゲームメーカー日本ファルコム様のものを使用させて頂いております。
録音機材
- SAMREC HATS Type2500RSシステム:HEAD & TORSO、Type4172マイクX2搭載
- 5055Prot 実時間2ch 自由音場補正フィルター(特注)
- マイクプリアンプ:Type4053
- Type5050 マイクアンプ電源
- オーディオインターフェース:ROLAND Rubix 24
- レコーディングソフト:Audacity
Tri Starseaのレコーディングシグネチャーは以下の記事に掲載されています。
総評
Tri Audio Starseaは1万円台に殴り込んできた恐るべきルーキーで、もしかすると台風の目になるかも知れません。それは完全にFiiO FH3と競合します。より風通しが良く、音場の広さはFiiO FH3を凌駕し、また音の質感的なナチュラルさでも、Tri Starseaのほうがより優れて感じられる可能性が高いです。音質変更スイッチの効果についてはとりあえず保留しますが(知りたい人は有料記事読んでね!)、デザイン的にもより万人受けするように思われますし、ビルドクオリティやパッケージにも不足がありません。
【関連記事】